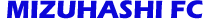水橋杯で一番頑張ってた21期(2年)の女の子が、腕をケガして大泣きして救急車で運ばれたと聞きました。
痛い思いに懲りてサッカーやめなきゃいいのにと心配しましたが、全然見当違いでした。ギプスをはめ、スパイクを履いて早速練習に来てました。
ゲームはできないので、進んで球拾いしてコーチを手伝ってくれ、1人でできるコーンドリブルで積極的に練習してました。その姿がまたいい感じでした。
コーンドリブルは、1人でできるので自主練にはいいのですが、なかなか集中が続きません。モチベーションが高くないとすぐグダグダになってしまうのが、彼女はピリッとしてましたね。感心しました。
少年たちにも是非見習っていただきたいものです。

***
「コーンドリブル」の話題のついでです。
サッカーのトレーニングについてのマニアックな話に興味のある方はどうぞ。
***
他のチームのコーチやサッカー経験のあるお父さんが水橋FCの練習を見たら、少年サッカーの練習の定番である「コーンドリブル」「ジグザグドリブル」をほとんどしないことに気づかれると思います。
しっかり理由がありまして、
サッカーのトレーニングの方法論は「アナリティック(analytic)トレーニング」と「グローバル(global)トレーニング」の2種類に分けることができ、水橋FCはグローバルトレーニングを採用しているからです。
【アナリティックトレーニングとは】
- サッカー(特に育成年代)で大切なのは「個の技術(テクニック)」だと考えます。そのため、サッカーの中にある特定の動作(テクニック)を切り取って、その動作を繰り返し練習します。ドリブルの練習であればコーンドリブルやシザース、ダブルタッチなどの反復練習。パスの練習であれば向かい合ってのインサイドキックの練習など。
- トレーニングによって選手を「育てる」と考える傾向があります。
- 成長を段階的に考える傾向があります。ジュニアの時にしっかり基礎を固めて、中学で・・・高校で・・・といった感じです。
【グローバルトレーニングとは】
- サッカーで大切なのは「サッカーをすること」だと考えます。そのため、トレーニングの中でゲーム(8対8,11対11)とほぼ同じ状況を再現させ、ゲームに内在する多くの要素を同時に練習します。少人数でのミニゲーム形式が練習の中心となります。
- トレーニングによって選手が「育つ」と考える傾向があります。
- 金太郎アメ的に考える傾向があります。ジュニアでもトップチームでも、どこで切ってもほぼ同じプレースタイル、トレーニングとなります。年齢とともに金太郎アメが大きくなるといった感じです。
【長所と短所】
≪アナリティック≫
(+)特定のテーマに集中してトレーニングするので、効果が目に見えやすい
(+)反復練習が主になるので、より多くの回数をこなすことができる
(-)特定のテクニックを身につけてもゲームで応用できないことがある
(-)選手のモチベーションを保つのが難しい
≪グローバル≫
(+)テクニック、戦術、体力を同時にトレーニングできる
(+)選手のモチベーションを高く維持することができる
(+)テクニック以外の「認知」「判断」といった要素を学ぶことができる
(-)効果が目に見えるまで時間がかかる
(-)反復回数が少ない
(-)トレーニングのコントロール(オーガナイズ)が難しい
【それぞれの起源】
私の知る範囲では、アナリティック派の起源は1970年代から根強い人気の「クーバーコーチング」です。
ホームページから引用すると
『ウィール・クーバーは偉大なプレーヤー達の動きをスローモーション・ビデオで分析した結果、彼らの一つ一つの動きやコントロール技術は、分解して殆どのプレーヤーにも教えることができるのだという結論に達しました。そこで考え出されたのがクーバー・コーチングのメソッドです』
一方のグローバル派の起源はオランダサッカー協会の育成ビジョン(1985年)です。ダッチビジョンとも呼ばれてます。
『トレーニングは、ボール、相手、味方、ゴールの4つが揃ったミニゲームで十分である』
ちなみにクーバーさんはオランダ人です。そのクーバートレーニングについて、オランダサッカー協会が『私たちの考えはクーバー氏のものとは違う』『一つ一つの動きを切り離してトレーニングしても、後で統合することはできない』とわざわざ明言するほど、両者の立場は異なります。
【これまでの経緯】
日本では圧倒的にアナリティック派が主流でした。日本サッカー協会の指導方針も「個」の育成に重きを置いてきました。2006年ドイツW杯の惨敗を分析し、「個々の能力の差」を大きな要因に上げ、指導マニュアルにも強く反映させました。
また、現在コーチをされている方の現役時代は、テクニック、個人技の反復練習がメインだったと思います。
したがって、新たにボランティアコーチを始める方はまずアナリティック派からスタートすることになります。
自分がどっち派なのか認識されてない方の多くもアナリティック派だと思われます。
しかし、ここ4,5年で少し流れが変わって、グローバル派が増えてきているように思います。
グローバル派が主流のオランダ・スペインのコーチが来日して研修会を開いたり、オランダ・スペインで学んだ日本人のコーチが日本に帰ってきて情報を発信している影響が大きいと思います。
【つまり何なんだ?】
アナリティックとグローバル。
傍から見たらどーーーでもいいような違いですが、指導者にとっては大きな違いなんです。
例えばブラジルW杯で同じ試合を見たとしても、アナリティック派は「ロッペン」「メッシ」「ネイマール」の活躍で自分たちが正しいと確信します。やっぱり「個人の能力」が大切だと。
グローバル派は「スペイン」の予選敗退にはビビったものの、「ドイツ」の圧勝で自分たちが間違ってないと確信します。「(個人に対する)フットボールの勝利」だと。
しかし、ジュニア年代の指導方法として、どちらが正しいかは分かりません。
2年生から6年生までアナリティック派でトレーニングを受けたA君と
2年生から6年生までグローバル派でトレーニングを受けたA君の成長を
比較することはできないので、正解を確かめようがありません。
結果に大きな違いがあるかもしれません。ないかもしれません。
なので、水橋FCのような街クラブのチームにとっては、実はどっちでもいいんです。
大切なことは、チーム内でコーチ陣が共通の方針を持っていることだと思います。
もし同じチームにアナリティック派とグローバル派のコーチがいたら、チームにとっても選手にとっても不幸なことになるでしょう。
残念ながらボランティアのコーチが集まるチームでは「あんな練習(あのコーチ)じゃダメだ」というチーム内の対立はよくある話です。最悪の場合、チームが分裂します。
しかしコーチ陣がどちらかにまとまっていれば、チームは何とかやっていけるでしょう。
水橋FCでは、数年かけて「グローバル」で統一するための取り組みを行ってきましたので、あと数年は何とかやっていけるでしょう。田原