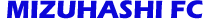現代サッカーは文字通り年々進化していて、見て飽きることがありません。
またそのサッカーを分析する方面でも進歩しており、詳細なデータを活用してチームの戦術に活かせるようになってます。高いお金を払ってデータ分析会社と契約すれば、ですが。
選手の走行距離、スプリントの回数、ポゼッション率などのデータは、もはやデータ分析会社の「売り物」ではありません。「守備時と攻撃時に分けた走行距離」、「全力に近いスプリント回数と距離」、「長いパス成功率」、「短いパス成功率」、「ピッチのエリア別のパス成功率」「アクチュアルフォーメンション」などなど。プレー中の選手は丸裸同然です。
「サッカーはシステムでは勝てない」の著者でサッカーアナリストの庄治さんによれば、今現在、チームの成績(長期のリーグ戦)に最も反映されているデータは「つなぐ意思」だそうです。(日本経済新聞:7月5日)
「パス成功数」=パスが成功した回数
「パス成功率」=「パス成功数」÷「パスを試みた数」
「つなぐ意思」=「パス成功数」÷「ボールに触れた数」
「パス成功率」の分母は「パスを試みた数」で、ドリブルやクリアなど、パス以外のプレーは除きます。
極端な例で紹介すると、
味方から10回パスを受けて、そのうち8回はドリブルを始めて、ボールを奪われるかシュートで終わり、残り2回は味方にパスをつないだ場合。この選手の「パス成功率」は100%。
一方、「つなぐ意思」の分母は「ボールに触れた回数」ですので、同じ選手の「つなぐ意思」は20%になります。
で、この数値が高いほど、チームの成績が上位にくるそうです。
昨シーズンのバイエルンミュンヘンの「つなぐ意思」は68%。
カナダワールドカップでのなでしこは57%(準決勝までの平均)で参加国の中で断トツです。
庄司さんによれば、なでしこのサッカーは、
「『ちゃんとフットボールをしましょう』という意識づけがしっかりされている」
「パスをつなげるポジション、ボールを失ってもすぐ取り返せるポジション、取り返したときにパスをつなげるポジションを取っていないと、これだけの数値は出ない」
スピード、パワー、テクニックが男子高校生レベルだったとしても、なでしこのサッカーの方が何倍も面白く感じるのはこの辺に理由があるのだと思います。
パスばっかりのプレーを見せられると「目的はパスをつなぐことじゃない。ゴールだ」と言いたくなることがあるのですが、現代サッカーでは正論とは言えないかもしれません。
そうは言っても、「つなぐ意思」では上回っていたなでしこも、米国に惨敗しましたけどー